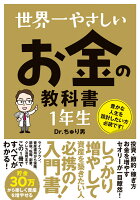おはようございます。
本日は、東証ETFのiFreeETF FANG+(316A)をご紹介します。
FANG+と言えば、投資信託のiFreeNEXT FANG+インデックスが大人気ですが、316AはそのETF版です。
2025年1月10日に上場したばかりの比較的新しい商品なので、ご存じない方も多いかもしれません。
316Aの最大のメリットは、信託報酬が年0.605%と投資信託版(年0.7755%)よりも安いことです。
お忙しい人向けに、60秒でサクッと学べるショート動画も用意しました。
よろしければどうぞ!
iFreeETF FANG+(316A)はFANG+指数に連動する国内ETF
iFreeETF FANG+の投資対象はFANG+指数
iFreeETF FANG+の投資対象は、FANG+指数です。
FANG+は、時価総額が世界トップクラスの米国ビッグテック10銘柄に10%ずつ均等に投資する指数です。
構成銘柄は、Meta(Facebook)、Amazon、Netflix、Alphabet(Google)、Apple、Microsoft、Nvidia、CrowdStrike、ServiceNow、Broadcomです。
このうち、FAANMG 6社は基本的に固定されており、残りの4社が業績などによって銘柄入れ替えの対象となります。
FANG+が投資家から人気を集める理由
FANG+がなぜ投資家から人気を集めているかというと、直近10年くらいの米国株を牽引してきたのがこれらビッグテックだからです。
実際、ビッグテックの株価上昇率はS&P500をはるかに凌駕しており、過去10年で株価は約7.3倍に急騰しました。
FANG+は「勝ち組厳選」による高リターンを狙う指数と言えます。
もちろん、これらビッグテックが将来的にも勝ち組のままでいられるかは分かりません。
また、テック集中投資になるので値動きが大きく、初心者向けではない点にも注意が必要です。
ビッグテックの圧倒的シェアと強さ
FANG+がなぜこれほど強いのでしょうか?
それは、FANG+の構成銘柄が、ネット検索、クラウド、SNSなどの主要なIT系サービスをほぼ独占しているからです。
また、FANG+を構成するのはたった10銘柄であるにもかかわらず、この10銘柄だけで米国株時価総額の約25%を占めています。
このように、FANG+は銘柄数こそ少ないものの、1社1社の存在感が群を抜いており、その圧倒的なシェアによって安定した収益を生むため、高リターンにつながっています。
iFreeNEXT FANG+インデックスとの比較と316Aの優位性
FANG+への投資を考えた場合、日本国内で一番有名かつ売れているのは「iFreeNEXT FANG+インデックス」だと思います。
発売開始が2018年1月と古く、純資産額も7,900億円と個人投資家からも非常に人気が高い商品です。
新NISAのつみたて投資枠でも選べる点も大きいのでしょう。
では、今回ご紹介する「iFreeETF FANG+(316A)」をわざわざ選ぶ意義は何でしょうか?
それは、信託報酬が年0.605%と投資信託版FANG+(年0.7755%)よりも0.17%ほど安いからです。
316Aは国内ETFなので、投資信託と比べると利便性はやや劣ります。
しかし、米国ETFのようにドルへの両替などは必要なく、1口2,000円程度から少額投資できるのは大きなメリットです。
新NISAは成長投資枠のみ対象となっています。
FANG+投資のリスクとコア・サテライト戦略
FANG+ですが、たった10銘柄への集中投資で、ボラティリティが相当に高いため、初心者向けの指数とは言えません。
投資のコアはオルカンやS&P500などの市場平均インデックスでがっちり固め、サテライト投資の対象としてFANG+を使うのがよいでしょう。
ポートフォリオ全体の10%以内でスパイス的に使うのがよいかもしれません。
積立投資でFANG+を活かす長期運用の可能性
もう1つ重要な点は、FANG+のように値動きの大きな銘柄ほど、積立投資向きということです。
一気に大金を投じて勝負するのではなく、コツコツと毎月積立を続けていけば、将来的に大きなリターンが期待できます。
実際、もしFANG+に10年前から毎月10万円積立投資した場合、投資元本1,200万円に対して、最終評価額は7,190万円と約6,000万円近い利益が出ています。
FANG+は長期目線で保有するのに適した指数と言えるでしょう。
まとめ:FANG+はサテライト投資に最適!iFreeETF FANG+(316A)でビッグテックに効率投資
iFreeETF FANG+(316A)は、人気のFANG+指数に低コストで投資できる国内ETFです。
投資信託版よりも信託報酬が安いのが魅力ですが、10銘柄に集中投資するため値動きが大きい点には注意が必要です。
コア資産はオルカンやS&P500で安定させつつ、サテライト投資として長期の積立に活用するのが賢い戦略でしょう。
もっと知識を深めたい方へ:著書のご紹介
『世界一やさしいお金の教科書 1年生』
お金の仕組みや基本的な考え方をやさしく整理。貯蓄・投資の第一歩を踏み出すために、誰もが知っておきたい知識をまとめました。
『世界一やさしい投資信託・ETFの教科書 1年生』
投資信託・ETFの選び方からNISA・iDeCoでの実践活用まで、初心者が迷わず投資を始められる1冊です。
関連記事のご紹介
今絶好調の金!ゴールドに低コストで投資するならSBIのサクッと純金がおすすめです。
VYMに間接的に投資できるおすすめファンド2選を解説しました。
NASDAQ100に投資するなら、信託報酬が0.11%と圧倒的低コストの2840がおすすめです。